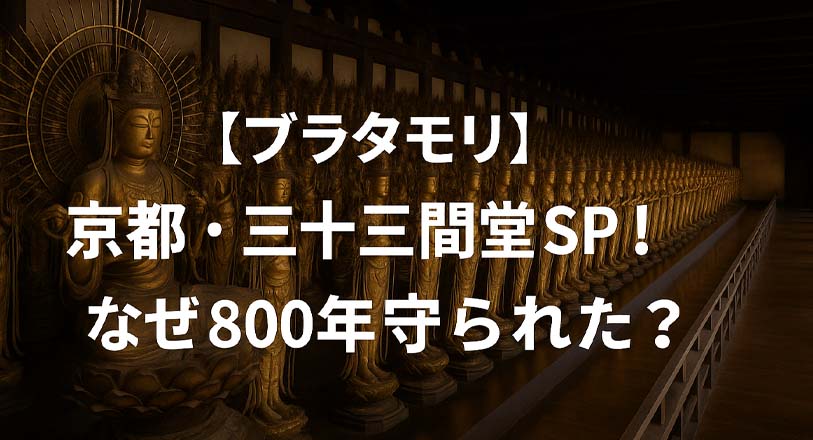
2025年9月20日放送の「ブラタモリ」<京都 国宝・三十三間堂SP/超拡大版!なぜ800年守られた?>では、千体の観音像と本堂がすべて国宝の三十三間堂を舞台に、数々の危機を乗り越えた“守り”の知恵と工夫を深掘り。秀吉の“京の大仏”との関係や、夜間特別公開の幻想的な観音像の姿にも迫ります。詳しいガイドは三十三間堂執事の大道観健さんでした。
京都・三十三間堂SP!国宝を守り続けた驚きの秘密
東大門かいら入場
今回は特別に東大門から入りました。普段はこちらの門は締切になっていて1年に1度だけ最大の法要がありその日1日だけ開けている門とのこと。
千体の観音像が並ぶ“国宝の堂”とは
三十三間堂は平安時代後期、後白河上皇の院政期に創建され、現在の本堂は鎌倉時代に再建されたものです。全長約120mの巨大な本堂の中には、千体もの千手観音立像が整然と並び、その中央には本尊の千手観音坐像が安置されています。堂内は静謐で荘厳な雰囲気に包まれ、訪れる人々を圧倒します。本堂も仏像もすべて国宝に指定され、まさに「国宝の宝庫」と呼ぶにふさわしい存在です。
地震・火災・戦乱をくぐり抜けた“耐震構造と地盤改良”
約800年の長い歴史の中で、三十三間堂は大火や地震、戦乱など幾度も危機に直面しました。しかし、本堂は地震の揺れを逃す「しなやかな構造」を備え、柱や梁が互いに力を分散する工夫がなされています。また、地盤が弱い京都盆地において、地盤を固めるための改良も施されており、これが長きにわたって建物を支える要因となりました。先人たちの知恵と技術の積み重ねが、現在まで三十三間堂を守り抜いてきたのです。
秀吉の“京の大仏”が三十三間堂を守った?意外な歴史の連関
豊臣秀吉が造営した「京の大仏」(方広寺大仏)は、かつて三十三間堂と隣接して存在していました。秀吉はこの大仏を中心に寺域を整備し、その結果、三十三間堂周辺も大規模に護られる形になりました。大仏はやがて地震や火災で失われましたが、その建設と維持の過程で整えられた環境が、結果的に三十三間堂の保存にもつながったと考えられています。豊臣権力の象徴であった大仏が、意図せず三十三間堂を守る役割を果たしたというのは、歴史の面白さを感じさせます。
タモリも言葉を失う…夜空に輝く観音像の特別公開
番組では特別に、夜間にライトアップされた観音像の姿が公開されました。昼間の厳かな雰囲気とは異なり、闇の中に金色の仏像群が浮かび上がる様子は幻想的で、まるで極楽浄土の光景のよう。タモリさんも思わず言葉を失うほどの美しさだったそうです。通常は見ることのできない三十三間堂の夜の姿は、視聴者にとっても貴重な体験となりました。

